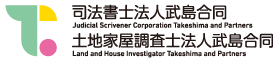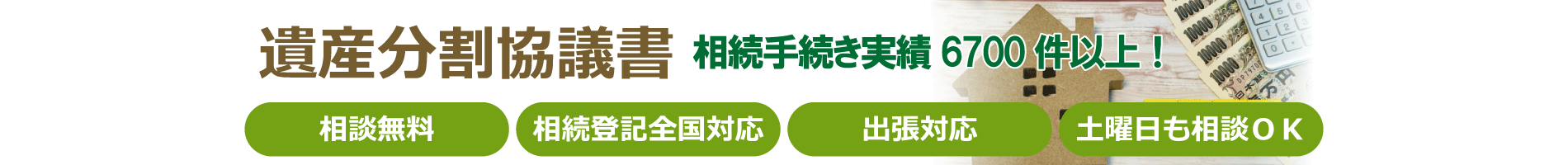遺産分割協議書の作成

相続が発生して複数の相続人がいる場合に、相続人全員で相続財産をどのように分けるか話し合い(協議)を行い、その協議の内容を「遺産分割協議書」という形で残しておくことで、将来のトラブル防止のために役立ちます。このページでは、遺産分割協議書の概要から、作成の流れ、費用、注意点まで詳しくご紹介いたします。
遺産分割協議書とは
遺産分割協議書とは、相続人全員で亡くなられた方の財産をどのように分けるかの話し合いを行い、その合意した内容を記録した文書です。不動産の名義変更や預貯金の解約手続きなどで必要となることがあります。遺産分割協議書を作成するには相続人全員の署名・捺印または記名・押印が必要となり、内容に不備があると手続きが進まないことがあるため、正確な作成が求められます。
遺産分割協議書作成がおすすめな方
| ◎相続人が2人以上いる場合 |
| ◎被相続人名義の不動産や預貯金などがある場合 |
| ◎法律で定められた割合と異なる割合で相続したい場合 |
| ◎相続財産の内容や分配方法を明確にして書類に残しておきたい場合 |
遺産分割協議書作成でよくあるお悩み・ご相談
遺産分割協議書の作成に関しては、次のようなお悩みを多くお聞きします。
- 相続人全員で話し合いをしたが、話がまとまらない
- 相続人の一部が遠方に住んでおり、協議書への署名押印の進め方が分からない
- 不動産や預貯金などの財産の分け方をどう書けばよいか分からない
- 書式や記載内容が正しいか不安で先に進めない
- 協議書を作成しても、相続登記や手続きで受け付けてもらえるか心配
遺産分割協議書の作成については、まずは状況整理からご相談いただけます。
「どこから手を付ければよいか分からない」といった段階でも、お気軽にご相談ください。
また、相続の状況によっては、相続放棄を検討した方がよい場合もあります。あわせてご確認ください。
遺産分割協議書作成に必要な書類
| ◎亡くなられた方の出生から死亡までの除籍謄本 |
| ◎亡くなられた方の住民票の除票または戸籍の附票 |
| ◎相続人全員の戸籍謄本 |
| ◎遺産の内容を示す資料 |
| など |
遺産分割協議書作成の流れ
- ご相談・ヒアリング
- 内容を丁寧にお伺いし、ベストのご提案をいたします。

- 必要書類の収集
- 遺産分割協議に必要な書類等を準備します

- 協議内容の確認・整理
- 重要な協議内容の確認となります

- 遺産分割協議書の作成
- 協議内容に基づき遺産分割協議書を作成します

- 相続人全員の署名捺印または記名押印
- 遺産分割の証となります

- 不動産の名義変更や預貯金の解約手続き
- 遺産分割協議書に基づき手続きを進めます

遺産分割協議書作成を司法書士に依頼するメリット
法的に有効な書類が確実に作成できる
司法書士は法的に有効な遺産分割協議書を確実に作成します。形式不備による手続きミスを防ぎ、安心して手続きを進められます。
煩雑な戸籍の収集や書類作成を代行
忙しい方でも安心して任せられます。戸籍の収集や必要書類の作成を司法書士が代行し、手間を大幅に減らします。
相続手続き全体を一括サポート
遺産分割協議書作成後も、不動産の名義変更や預貯金の解約手続きなど、相続手続き全体を一括でサポートし、スムーズに手続きを進めることができます。
遺産分割協議書作成は当事務所「司法書士法人武島合同」へ!
遺産分割協議書作成に強い司法書士が複数在籍しております。相談から遺言書作成完了まで、丁寧にご対応いたしますので、安心してお任せいただけます。

司法書士 川中辰介
大阪司法書士会登録番号 2449

司法書士 細田真弘
大阪司法書士会登録番号 4602

司法書士 巽菜保子
大阪司法書士会登録番号 5050

司法書士 中越俊輔
大阪司法書士会登録番号 5190

司法書士 種川愉
大阪司法書士会登録番号 5290
相談無料・土曜日も面談可
忙しい方も安心。ご自身の都合に合わせてご相談いただけます。土曜日もご相談を承っています。出張面談も可能。
面倒な手続を一括代行
複雑な手続きをワンストップで解決。当事務所では相続の専門家が面倒な手続きを一括代行いたします。
相続に強い専門家
経験豊富な専門家(司法書士)が複数在籍。遺産分割協議書作成をはじめ相続手続き、相続登記、相続放棄、遺言書作成など幅広いサポートが可能。
遺産分割協議の相談事例
遺産分割協議に参加できない相続人がいる場合①
- 遺産分割協議に参加できない相続人がいる場合
- 祖母が亡くなり相続手続きをするため、戸籍等を集め、遺産分割の準備を進めていたところ、相続人のうち、叔父が認知症で意思表示ができず遺産分割ができないことが判明し、どうしたらいいのかというご相談です。
- 司法書士法人武島合同での解決策
- 認知症の相続人が遺産分割協議を行うには「成年後見制度」を利用する必要があります。家庭裁判所が選任した成年後見人が認知症の相続人に代わって遺産分割協議を行うことになりますので、今回の場合は、当事務所で成年後見人の申立てを代行し、家庭裁判所で成年後見人が選任され、無事遺産分割協議を済ませることができました。
相続手続きはこちら>>
遺産分割協議に参加できない相続人がいる場合②
- 遺産分割協議に参加できない相続人がいる場合
- 夫が亡くなり相続手続き進めているが、相続人である二人の子のうち、一人が未成年者であるため遺産分割ができないことが判明し、どうしたらいいのかというご相談です。
- 司法書士法人武島合同での解決策
- 未成年者については、親権者が代理人として遺産分割協議を行うことになりますが、相続の場面では、通常は親権者自身も相続人となっているケースがほとんどです。その場合は親権者と未成年者が「利益相反状態」にありますので、法律上、親権者が子を代理することができません。このような場合、親権者に代わって子を代理する「特別代理人」の選任を家庭裁判所に申立てる必要があります。
今回の場合は、当事務所で家庭裁判所に特別代理人の選任の申立てを代行して行い、その結果、特別代理人が選任され、無事遺産分割協議をすることができました。
相続手続きはこちら>>
お客様の声
遺産分割協議書の作成
以前の父の相続の時に、私たち4人の兄弟の間にわだかまりが出来ていました。
貴事務所に相談したところ、親身になって丁寧に相談にのっていただきました。
わざわざ遠方の私の自宅にまで来ていただき、兄弟4人の話し合いに同席していただきました事を感謝しています。
私も含めて相続人である4人の思いが重要であることをご指摘いただき、それを承知の上であればということで、法律家として同席していただき大変心強く感じました。
おかげさまで無事、母の遺産分割協議も終えることが出来、不動産を含め預貯金等々の相続関係手続きもお願いできて良かったです。
4人の兄弟の間のわだかまりも無くなり、スムーズに相続手続きを完了していただき大変感謝しております。
ありがとうございました。
大阪府 65歳 男性
遺産分割協議書作成の注意点
- 相続人全員の合意が必要
- 一人でも遺産分割の協議内容に同意しない相続人がいると遺産分割の協議は成立しません。
- 記載内容の不備に注意
- 不動産の表記ミスや相続人の誤記載があると手続きができない恐れがあります。
曖昧な表現は避け、財産の配分を正確に記すことが大切です。
- 押印は実印で行うこと
- 遺産分割協議書を提出して手続きを行う場合に遺産分割協議書への実印の押印と印鑑登録証明書の提出が必要な場合があります。
遺産分割協議書に関するよくある質問
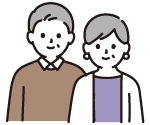
遺産分割協議書は自身で作成しても大丈夫ですか?

ご自身で作成することも可能でありますが、形式の不備や内容の誤りにより手続きが滞るリスクがあるため、司法書士など専門家への依頼をおすすめします。
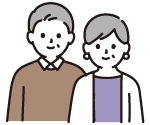
相続人の一人が協議に応じない場合はどうしたらいいですか?

遺産分割協議は相続人全員での合意が必要なため、もし協議に応じない相続人がいる場合には家庭裁判所での調停や審判が必要になることもあります。
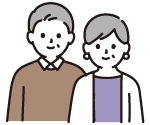
遺言書がある場合でも遺産分割協議をすることができますか?

遺言書がある場合でも、相続人全員の同意があれば遺産分割協議をすることができます。ただし、遺言書で遺言執行者がいる場合には、相続人全員の同意だけでなく遺言執行者の同意も必要となります。
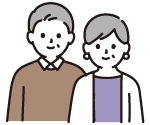
遺産分割協議書は何部作成するべきですか?

原則として、相続人の人数分+名義変更手続き用に複数部作成しておくと安心です。