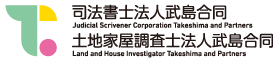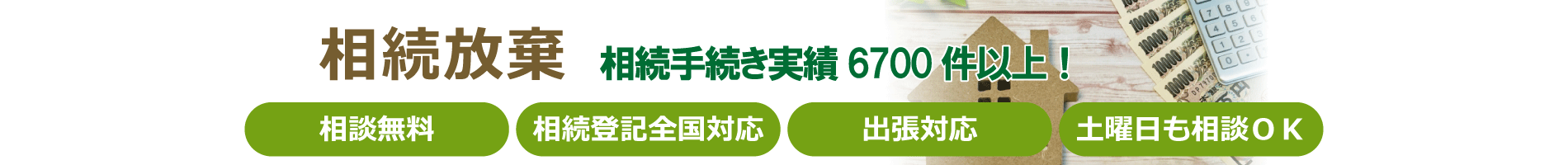相続放棄手続き

相続が発生した場合、亡くなられた方が遺した財産(遺産)は相続人が引き継ぐことになります。遺産には預貯金や不動産などのプラスの財産もありますが、借金などのマイナスの財産も含まれます。そこで、亡くなられた方の遺産を相続しないための手段として相続放棄というものもあります。
ここでは、相続放棄に関する基本的な知識から、手続きの流れ・費用・必要書類など、詳しく解説します。
相続放棄とは
相続放棄とは、相続人が亡くなられた方(被相続人)の全ての遺産(預貯金や不動産、借金など)を受け継がないことを選択する法的手続きです。家庭裁判所に申述書を提出し、受理されることで正式に相続放棄が成立します。
相続放棄が成立すると相続放棄した人は、その相続に関して初めから相続人とならなかったものとみなされます。
なお、相続放棄は被相続人の全ての遺産を放棄する手続きであり、預貯金は欲しいが不動産は要らないので不動産だけを相続放棄するというようなことは出来ません。
相続放棄でよくあるお悩み・ご相談
相続放棄に関するご相談では、次のようなお悩みを多くいただいています。
- 被相続人に借金があると聞いたが、本当に相続放棄が必要なのか分からない
- どこまで調べれば「相続放棄すべきか」を判断できるのか不安
- 相続放棄の期限があると聞いたが、自分のケースが該当するのか判断できない
- 一度手続きを進めてしまってからでも、相続放棄ができるのか知りたい
- 相続放棄をすると、他の相続人や家族にどのような影響があるのか心配
相続放棄については、判断に迷っている段階からご相談いただけます。相続放棄が本当に必要かどうか、手続きを進めるべきかも含めて、状況に応じてご案内いたします。
また、相続の状況によっては、相続放棄ではなく、遺産分割協議や相続登記など、別の手続きを検討した方がよいケースもあります。
相続放棄の条件
相続放棄には、次のような条件があります。
◎相続が開始してから3か月以内に申述書を家庭裁判所に提出し、相続放棄が認められること。※3か月経過後であっても相続放棄が認められる場合もございます。詳しくはご相談ください。
◎相続財産の一部でも処分していないこと。(処分していると相続することを承認したとみなされる可能性があります。)
相続放棄がおすすめな人
◎被相続人に借金などの負債が多く、プラスの財産を上回るとき。
◎相続トラブルに巻き込まれたくないと考えている場合。
相続放棄の費用
一人当たり33,000円(税込)~ +実費
(※その他の戸籍収集を当事務所で行う場合には、追加で実費と報酬が発生いたします。)
相続放棄に必要な書類
相続放棄手続きには以下の書類が必要です。
◎相続放棄申述書
◎被相続人の住民票除票または戸籍の附票
◎被相続人の死亡が記載された戸籍謄本
◎申述人(放棄する人)の戸籍謄本
※被相続人と相続人との関係によって追加書類が必要となる場合があります。
相続放棄の流れ
- 1.ご相談・ヒヤリング
- 丁寧にお伺いいたします。

- 2.必要書類を揃える
- 裁判所に提出する為の必要書類を事前に準備

- 3.相続放棄申述書を作成
- 提出書類の作成

- 4.管轄の家庭裁判所へ提出
- 裁判所からの照会書への回答

- 5.相続放棄の受理通知を受け取る
- 相続放棄手続きの完了

相続放棄の注意点
相続放棄を行う際には、以下の点に注意が必要です。後々のトラブル回避の為に知っておくことが大切です。
- 相続が開始してから3か月を過ぎると相続放棄が認められない。
※ただし、事例によっては、3か月経過後であっても相続放棄が認められる場合もあります。詳しくはご相談ください。
- 財産の一部でも使用・処分してしまうと、相続することを承認したとみなされて相続放棄できなくなる可能性がある。
- 他の相続人への影響(相続人の変動)に注意。
※相続放棄をすることによって、次順位(被相続人の兄弟姉妹や他の親族)の方が相続人になる場合があります。
- 相続放棄後に相続放棄の撤回はできない。
相続放棄の手続きを司法書士に依頼するメリット
相続放棄は、自分でも手続きを進めることは可能ですが、手続きの複雑さや期限の厳守を考えると、司法書士に依頼することで多くのメリットがあります。
- 書類の不備や記入ミスを防げる
- 相続放棄に必要な書類には、戸籍謄本や住民票除票、申述書などがあります。これらを正確にそろえ、誤りなく記入するのは意外と大変です。司法書士に依頼すれば、必要書類の案内から記入方法の指導まで一貫してサポートを受けられ、書類不備による再提出を防げます。
- 裁判所とのやり取りも任せられる
- 家庭裁判所から照会書(質問書)が届くことがありますが、内容によっては回答に悩むことも。司法書士に依頼しておけば、どのように回答すべきかアドバイスをもらえるため安心です。
- 短期間で確実に手続きが進む
- 相続放棄には「相続が開始してから3か月以内に家庭裁判所に書類提出しなければならない」という厳しい期限があります。専門家に依頼すれば、必要な手続きを効率よく進めてもらえるため、期限内にスムーズに対応できます。
- 戸籍の収集や面倒な手続きを代行してもらえる
- 戸籍など必要書類を揃える作業は、慣れていないと時間も手間もかかります。司法書士に依頼すれば、このような面倒な作業を代行してもらえるのも大きなメリットです。
- 他の相続人とのトラブルを防げる
- 相続放棄は他の相続人にも影響する可能性があるため、手続きのタイミングや連絡の仕方に注意が必要です。専門家のアドバイスを受けながら進めることで、誤解やトラブルを未然に防ぐことができます。
相続放棄手続きは当事務所「司法書士法人武島合同」へ!
相続放棄に強い司法書士が複数在籍しております。相談から相続放棄の手続き完了まで、丁寧にご対応いたしますので、安心してお任せいただけます。

司法書士 川中辰介
大阪司法書士会登録番号 2449

司法書士 細田真弘
大阪司法書士会登録番号 4602

司法書士 巽菜保子
大阪司法書士会登録番号 5050

司法書士 中越俊輔
大阪司法書士会登録番号 5190

司法書士 種川愉
大阪司法書士会登録番号 5290
相談無料・土曜日も面談可
忙しい方も安心。ご自身の都合に合わせてご相談いただけます。土曜日もご相談を承っています。出張面談も可能。
面倒な手続を一括代行
複雑な手続きをワンストップで解決。当事務所では相続の専門家が面倒な手続きを一括代行いたします。
相続に強い専門家
経験豊富な専門家(司法書士)が複数在籍。相続放棄をはじめ相続手続き、相続登記、遺産分割協議書作成、遺言書作成など幅広いサポートが可能。
相続放棄の相談事例
被相続人に借金・債務がある場合の相続
- 亡くなった父が連帯保証人になっていた
- 会社を経営していた父が亡くなり、相続の手続きを進めていたところ、銀行から会社が借入れしている債務につき父が連帯保証人になっていることが分かり、どうしたらいいのかというご相談です。
- 司法書士法人武島合同での解決策
- 亡くなった方に借金がある場合には、各相続人が法定相続分に応じて返済義務を承継します。
遺言や遺産分割協議によって『特定の1人の相続人が借金をすべて相続する』としても、そのことを債権者が認めた場合を除き、お金を貸した債権者は法定相続分に応じた返済を各相続人に求めることができるので注意が必要です。今回の場合は不動産、預貯金等のプラスの相続財産より、借入金の負担の方が大きかったので、当事務所で相続人全員について家庭裁判所に相続放棄の申述を代行し、相続放棄することになりました。相続放棄を行えば、そもそも相続人ではなかったことになるので、借金を相続することはありません。相続放棄といっても遺産分割協議において、『一切の遺産を受け取らない。』としても、これは相続放棄ではありません。相続放棄をするためには家庭裁判所に申し立てて受理されなければなりませんのでご注意ください。
相続手続きはこちら>>
相続放棄に関するよくある質問
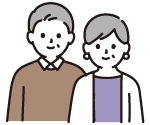
相続放棄は家族全員で行う必要がありますか?

いいえ、相続放棄は個人単位で行う手続きですので、お一人でも手続きすることができます。
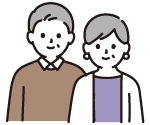
相続放棄をした後に通知は届きますか?

相続放棄が認められると、家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が届きます。
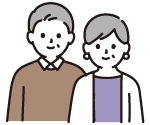
相続放棄は電話やインターネットでできますか?

書類を家庭裁判所に郵送または持参する必要があります。オンライン手続きには未対応です(2025年4月現在)。